マイホーム購入を考え始めたら最初に読むべきお金の基礎知識まとめ
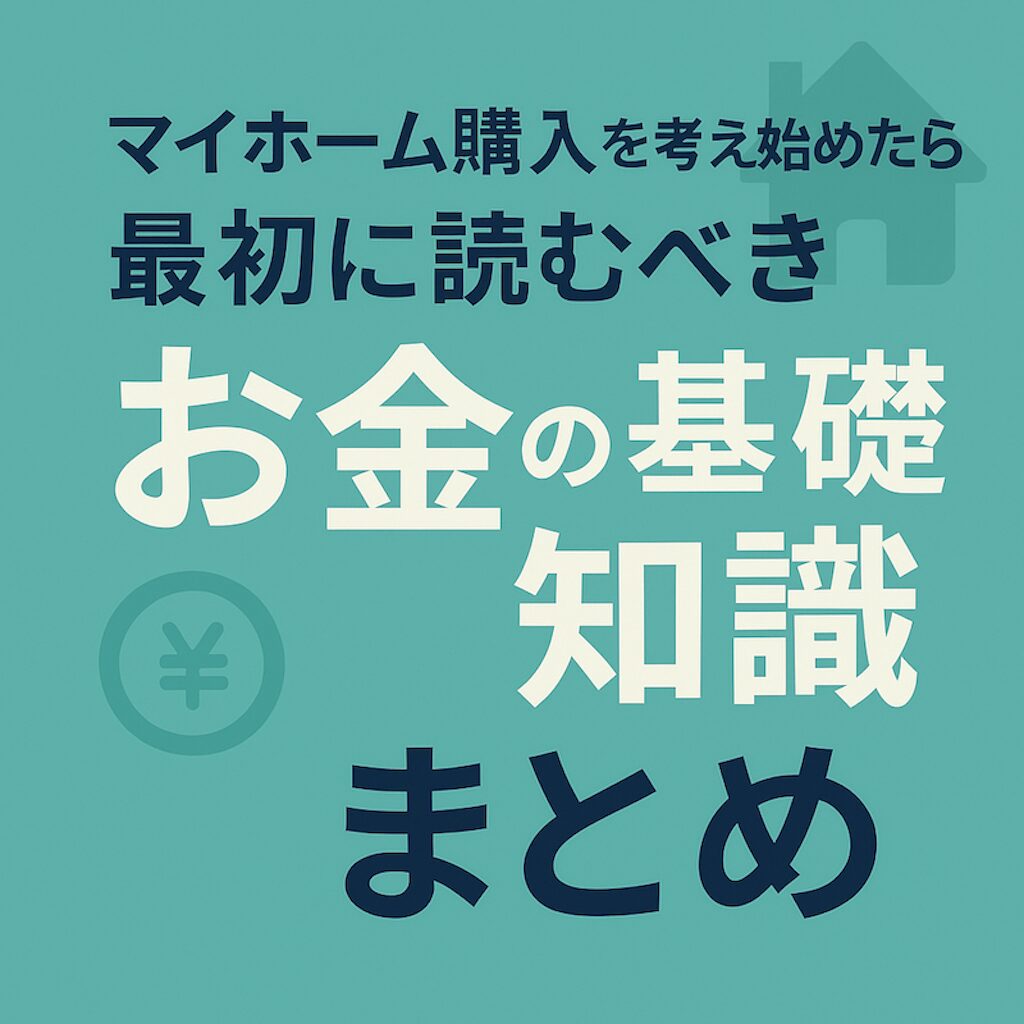
マイホーム購入を検討している方、特に子育て世帯だと、

「毎月家賃を払うくらいならいずれ自分のものになる家のローンにお金を使いたい…!」
「将来は資産として子どもに残したい!」
「子どもが自由に過ごせる空間が欲しい!」
と考える人も多いと思います。
しかし、その一方で、

「毎月余裕を持ってローン返済できるのか?」
「住宅購入予算はどう決めるべきか?」
「頭金なしでも家を買えるのか?」
など、お金に関する不安がつきものです。
しかし、多くの住宅営業マンはマイホーム購入後のことまで考慮したお金の相談には乗ってくれません。
そもそもお金のことを、知らない人に相談するのはかなりハードルが高いですよね。
実際に、私も25歳で一人目の子どもができたばかりのときに、なんの知識もなく勢いで注文住宅を契約しました。
そのため、実際に住宅ローンの返済がはじまると、ローン返済や生活費のやりくりにかなり苦労していました。
この記事では、そんな私の実体験をもとに「家を買う前に知っておきたかった最低限のお金の知識」を初心者向けにまとめています。
この記事を読むだけで、住宅ローンの返済に困ることなく、マイホームを購入できるようになります。
マイホーム購入を検討している方はぜひ最後まで読んでください。
(この記事では新築戸建住宅を、ハウスメーカーや工務店から購入することを前提としています。中古住宅やマンションを不動産会社から購入することは想定しておりませんので、あらかじめご了承ください。)
マイホームを持つと多くのリスクがある
マイホーム購入を考えている方にまず一番に知ってほしいことは、
「マイホームを購入すると多くのリスクを抱えることになる」
ということです。
特に注意したい代表的なリスクは以下の2点です。
- 購入後に資産価値が下がる可能性がある
- ライフスタイルの変化に対応しづらくなる
マイホームを持つ最大のリスクは資産価値が下がること
マイホームを持つことにはいくつかのリスクがありますが、中でも最も大きなリスクは「資産価値が下がること」です。
よく耳にする「住宅ローン破綻」も、実はこの資産価値の下落が一因となっているケースが多くあります。
多くの住宅は、購入した瞬間から資産価値が下がり始め、その後も下落を続ける傾向にあります。
たとえば、以下の画像のように、3,000万円で購入した住宅を1年後に査定してもらったところ、評価額(マイホームの価値)が2,500万円だったとします。

この場合、ローンの残債が3,000万円のままであれば、差額の500万円は「家を売却しても返済できない負債」を抱えることになります。
「住宅ローンが払えなくなったら、家を売ればなんとかなる」と考えている方も少なくありませんが、
このようにローン残高よりも住宅の資産価値が低い「オーバーローン」の状態では、差額を現金や他の資産で補填しなければ、家を売ることすらできないのが現実です。
このような負債を抱える可能性があることこそ、マイホーム購入の大きなリスクとなります。
さらに、住宅は築年数の経過とともに資産価値が大きく下がり、築20~30年を超えると建物部分の価値はほぼゼロになるケースもあります。
もちろん、都内の一等地など資産価値が下がりにくい優良物件も存在します。
しかし、そういった物件は不動産投資家や不動産会社などのプロが早い段階で押さえてしまうことが多く、私たち一般の購入者が手にできることはほとんどありません。

私は3,050万円で注文住宅を購入しましたが、3年後に住宅の査定をしてもらうと約2,250万円まで下がっていました。
3年後の住宅ローンの残債は約2,800万円なので、約550万円の負債を抱えていることになります。
ライフスタイルの変化に対応できない
マイホームを購入すると、転職や転勤、子どもの進学などで住環境に不満が出ても簡単に引っ越すことができません。賃貸であれば比較的柔軟に住み替えができますが、持ち家の場合は売却や賃貸化などの手続きが必要になり、思った以上に負担が大きくなることもあります。
マイホーム購入するならリスクを受け入れたうえで購入しよう
私が伝えたいのは、
「マイホームを購入するのはリスクが大きいから購入しないほうがいい」
ということではなく、
「多くのリスクを受け入れたうえで、それでも欲しい方は購入しよう」
ということです。
「マイホームは資産になる」
「賃貸に家賃を払い続けるのはもったいない」
「マイホームは住宅ローンを払いきれば自分のものになる」
といった“損得”だけに基づいた判断で購入するのではなく、
「子どもが自由に過ごせる空間が欲しい」
「夢のマイホームで家族との思い出を作りたい」
という思いであれば、マイホーム購入してもいいと思います。
マイホームは基本的に資産ではなく「贅沢品」です。
マイホームを持つことには大きなリスクがあることを前提に、それでも「家族のために」「自分たちの暮らしを豊かにするためにお金を使う」と考えることで、ご自身がより納得してマイホーム購入できることにつながります。
「持ち家or賃貸」生涯住むならどちらがお得?
「賃貸に家賃を払い続けるのはもったいない」
「マイホームは住宅ローンを払いきれば自分のものになる」
マイホームを検討している方は上記のように、持ち家のほうがお得と考えて購入しようとしている方も多いです。
しかし、「持ち家or賃貸」どちらがお得かは永遠のテーマであり、答えはだれにもわかりません。
どちらがお得と感じるかどうかは人それぞれの価値観であって、比べようがないからです。
以下は、持ち家の時の毎月の住宅ローン返済額と、賃貸の毎月の家賃を同じだった場合のシミュレーションをした表になります。
| 項目 | 持ち家(購入) | 賃貸(家賃) |
|---|---|---|
| 初期費用 | 約300万円(頭金・諸費用) | 約30万円(敷金・礼金など) |
| 住宅ローン総額 | 約4,700万円(元金4,000万円+金利1%/35年) | ― |
| 月々の支払い額 | 約113,000円(35年間) | 約113,000円(50年間、家賃として) |
| 固定資産税 | 約700万円(年14万円×50年) | ― |
| 修繕・リフォーム費 | 約1,000万円(50年間で複数回の修繕を想定) | ― |
| 家賃 | ― | 約6,780万円(113,000円×12ヶ月×50年) |
| 更新料 | ― | 約200万円(2年ごとに1ヶ月分想定) |
| 引っ越し費用 | ― | 約300万円(10年ごとに想定) |
| 合計費用 | 約6,700万円 | 約7,310万円 |
このシミュレーションを見ると、一見、金銭的には生涯持ち家に住んだほうがお得に見えます。
しかし、持ち家と賃貸の比較には、単純な金額だけでは語れない複数の要素が絡んでおり、その要素がすこし変わるだけで結果は大きく変わります。
- 住宅の立地や築年数
- 住宅ローンの金利
- 住宅の資産価値の上下
- 賃貸物件の老朽化による家賃値下げ
- 家族構成やライフスタイルの変化
- 転勤や転職の有無
こうした条件は一人ひとりまったく異なります。
さらにいえば、同じ物件はこの世に2つと存在せず、同じ人生を歩む人間もいません。
仮に全く同じ住宅を買う人が2人いたとしても、収入や生活スタイル、将来設計が異なれば「お得かどうか」の感じ方もまったく違ってくるため、比べようがありません。
住宅購入予算のたてかた
マイホームを購入すると決めたら、まずは住宅購入に充てられる予算(住宅ローン借入額)を明確にしましょう。
この予算によって、選べる立地や建てられる家の規模・仕様などがある程度決まってくるため、最初に決めておくことが重要です。
住宅購入の予算を考えるときに主に考えるべきことは、毎月余裕をもって返済できる範囲内に抑えるということです。
毎月余裕をもって返済できる住宅購入予算を割り出す方法として、大きく分けて以下の2つが挙げられます。
- 年収倍率から計算する
- 返済負担率を目安にシミュレーションする
年収倍率(年収の◯倍まで)から住宅購入予算をたてる
毎月余裕をもって返済できる住宅ローンの借入額を把握するための方法のひとつに、「年収倍率から割り出す方法」があります。
これは最もシンプルで分かりやすく、おおよその予算感をつかむには適した方法です。
一般的には、「年収の7倍以内」であれば、無理のない返済ができると言われています。
例:年収500万円 × 7倍 = 借入可能額 約3,500万円
ただし、この方法では具体的な月々の返済額や家計への影響が分からないため、実際にマイホーム購入を検討している段階では、この方法だけで判断するのは不十分です。
より正確な予算を把握するには、シミュレーションサイトを活用して、月々の返済額や返済負担率を把握しておくことが重要です。
シミュレーションサイトを活用して住宅購入予算をたてる
シミュレーションサイトを活用して、住宅購入予算を決める場合「返済負担率」を目安に計算するのがおすすめです。返済負担率とは、年収に対して年間の返済額の割合のことをいいます。
一般的に、住宅ローンの借入額は、
「年収負担率(年収の内の年間返済額の割合)25%以内」までなら安心と言われています。
例「年間返済額120万円(毎月返済額10万円)÷年収480万円=年収負担率25%」
私は実際に、年収負担率25%を目安に予算を立ててマイホームを購入しました。
しかし、いざ返済が始まってみると、生活は想像以上に厳しく、特に無駄遣いをしているわけでもないのに、赤字になる月もありました。
このことから、私個人的には「年収負担率(年収の内の年間返済額の割合)20%以内」または「年収の6倍まで」なら安心と感じました。
具体的なシミュレーション方法
住宅ローンシミュレーションサイトで、
「借入可能額の試算」の「年収より計算する」から、以下の条件を例に入力してシミュレーションしてみてください。
- 返済方法は? 「元利均等返済」
- 返済期間は?「35年」
- 当初金利は? 「1%」(今後上昇することも想定して1~2%)
- ご本人様の年収は?「ご自身の年収」
- 連帯債務者の年収は?「生計を共にしているご家族の年収」(主に配偶者の年収)
- 返済負担率は?「20%」
このシミュレーション結果の「借入可能額の算出結果」が余裕をもって返済できる住宅購入予算の目安となります。
なお、この予算では理想の家が購入できない場合は、無理に借入額を増やすのではなく、頭金を貯めてから購入することを検討してみてください。
頭金は必要?
マイホームを購入する時、一般的には、「頭金を物件価格の10%〜20%用意しよう」など、よく言われています。
しかし、わたしたち子育て世帯にとっては、教育費や生活費で出費も多く、頭金を入れるほどまとまったお金を用意するのは難しい場合が多いです。
そのため、「頭金を貯めてから買うべきか、今すぐ買うべきか」で悩む方は少なくありません。
頭金とは
頭金とは、住宅を購入する際に、住宅ローンを借りる前に自己資金として支払うお金のことです。
たとえば、4,000万円の物件を購入する場合、頭金として400万円(購入価格の1割)を用意すれば、残りの3,600万円を住宅ローンとして借り入れることになります。
頭金を多く入れるほど借入額が減るため、月々の返済額や利息負担も軽くなります。ただし、頭金を支払うことで貯金が減ってしまい、急な出費に対応できなくなるというデメリットもあります。
頭金は0円でもマイホームを購入できる
最近では、頭金を用意しなくても住宅ローンを利用できるケースが増えてきました。実際、私自身も頭金0円でマイホームを購入しました。金融機関によっては、頭金なしでフルローンを組める商品もあり、若い世代や貯蓄に余裕がない家庭でもマイホームを購入しやすくなっています。
予算が足りない時に頭金を入れよう
「住宅購入予算をたてかた」で解説したやりかたでシミュレーションして予算をたてても、実際にハウスメーカーに見積もりを作成してもらったら、どうしても予算を超えてしまうということもあります。
このような状況であれば頭金を貯めてから住宅購入することをおすすめします。
たとえば、シミュレーションで出た予算が4000万円であったとします。
しかし、購入したい理想の家が4500万円掛かる場合、頭金を約500万円入れて購入することで、返済負担率を20%以内に抑えることができます。
初期費用として手付金が必要
頭金は必要ないですが”手付金”が必要な事が多いです。これはハウスメーカーや工務店との契約時に支払うお金で、契約の意思があることを示す証拠金のようなもの。契約後に解約する場合はこの手付金を放棄することでキャンセルする(=手付解除)ことができます。
この手付金は契約をキャンセルしなければ購入金額の一部に充当されるため、無駄になるわけではありませんが、契約時点である程度の現金が必要である点には注意が必要です。
手付金の相場は、数十万円〜100万円前後であることが多いですが
初期費用を用意する
家を購入する際には、物件価格の他にもいくつか初期費用がかかります。主なものには以下があります。
- 手付金
- 登記費用
- 住宅ローン手数料・保証料
- 火災保険料・地震保険料
これら初期費用の多くは住宅ローンに含めて借りた後で支払うことも出来ますが、注意点として、「手付金」は住宅ローンに含められないので、ハウスメーカーと契約する時点である程度の現金が必要です。
初期費用として手付金が必要
手付金とは、ハウスメーカーや工務店との契約時に支払うお金で、契約の意思があることを示す証拠金のようなものです。契約後に解約する場合はこの手付金を放棄することでキャンセル(=手付解除)することができます。
ちなみに、契約後にハウスメーカー都合で解約された場合、手付金の2倍の額が返金されることが一般的です。
手付金の相場は、数十万円〜100万円前後であることが多いですが、ハウスメーカーによっては交渉して金額を下げてもらうことも出来ます。
この手付金は契約をキャンセルしなければ購入金額の一部(頭金)に充当されるため、無駄になるわけではありませんが、契約時点である程度の現金が必要になります。
「値下げしてもらった一次情報」
諸費用は住宅ローンに含められる?
住宅ローンの借入額に諸費用を含めて借り入れること(諸費用ローン)は可能ですが、すべての費用を含められるわけではありません。また、金融機関によって取り扱いが異なります。
一般的に住宅ローンに含めて借りられることが多い費用
- 保証料(または事務手数料)
- 住宅ローンの事務手数料
- 火災保険料(一定条件あり)
含められない/難しいことが多い費用
- 引っ越し費用
- 家具・家電の購入費
- 印紙代
金融機関は、住宅購入に直接かかわる費用のみをローンに含める傾向があります。登記費用や仲介手数料などは自己資金での支払いが求められることが多いです。
ただし、「諸費用ローン」や「フルローン」などの商品を提供している銀行もあり、これらの費用も含めて借り入れができる場合があります。希望する場合は、事前に金融機関へ確認しましょう。

